| [第一話へ][第三話へ] | ||
| ||
|
「鯖男、良く聞け。俺は、お前に鯖の心を知ってもらいたいからこそ、この名前を付けた。第一、鯛や平目などの高級魚なんかよ、うちの家庭には縁が無いだろ。」 飲んだくれの父親は、酒を飲む度に、こじつけのような訳の分からないことを言った。おそらく、命名する時だって飲んでいたのに違いない。多分、ツマミにシメサバなど食べていたのではないのか。いずれにしても、父親が死んだ今となっては、真相は闇の中である。 ただ、最近はこの名前も決して嫌いではない。若い女子社員などは、俺のことをサバちゃんと呼ぶ。近頃の若い者の考え方は分からんでもないが、なんと砕けた呼び方であろう。一昔前なら絶対に自分の上司をふざけた愛称で呼んだりはしなかった筈だ。おそらく、肩書きの何も無い俺だからこそ、そんな気安さもあるのだろうか。 だが、俺も三十五歳だ。いつまでもサバちゃんでは済まされない。出世欲などさらさら無いが、若い社員に親しみを持たれて喜んでいる場合ではないのだ。  まあ、多少の危機感は持っているにしろ、俺一人が騒いだところで、どうにもならない。むしろ、冬だというのに、光熱費が浮いていることに感謝すべきだろう。この季節は、快適だった。北風も気にならない。逆に、もう少し寒くなってくると、着膨れラッシュで返って汗をかくことのほうが多い。 俺の住んでいる幕張ベイタウンも、まったく季節感の無い街だ。元々、海を埋め立てた街なので、緑が少ない。人工的に作られた緑も、年中吹く潮風にやられて瀕死の状態なのだ。無機質なコンクリートのマンション街でも、緑との調和があれば美しい。立ち枯れた樹木らしきオブジェが並ぶだけでは、あまりにもみすぼらしかった。 碁盤の目のように規則正しく正方形の建物が鎮座する街の作りは、ヨーロッパの町並みにも通じるのだが、何か物足りなさを感じずにはいられなかった。それは、やはり緑の少なさなのだろうか。 著名な建築デザイナーが創った巨大なコンクリートの塊も、見方によっては、港湾に野積みしてあるコンテナと大差無い。 まあ、それでも、俺はこの街が気に入っているのだ。同僚から、ベイタウンが砂上の楼閣と揶揄されようが、一向に構わない。だからこそ、無理をして高いローンにあくせくしながら、ここに住んでいる。 俺は、窓から見おろす公園に目をやった。この季節には珍しく南西方向からの湿った海風が吹いていて、僅かに残った緑が揺れている。いい天気だった。 俺は、二人の息子を日曜日だけ面倒を見なくてはならないので、早起きし、パソコンを立ち上げていた。仕事に追われて、ろくに息子と遊ぶ暇も無いし、趣味の時間も全く取れない。何かをやろうとすると、日曜の朝しかないのだ。 日溜りの公園では早起きした子どもの声がコンクリートの街並みに反響して、こだましていた。 あれから一度、荷物の整理と称して、東京本社に顔を出した時に会ったきりだ。一ヶ月に一度家に戻ると言ってたが、鹿児島からじゃ、大変だろうし、飛行機代も自腹なのか会社持ちなのか知らないが、家計を逼迫するのは目に見えている。 「空を飛ぶように、ぱっと飛んで行けたら、左遷されようが、へいちゃらなんだがな。」送別会の席上、部長が自虐気味につぶやいた言葉だ。 部長という職にある者が、ずいぶんつまらないことを言うものだ。同僚たちは、ヤキがまわったと、陰口を叩いていたが、俺はそう思わなかった。自分に置き換えたら、どうだろう。そんな辺鄙な土地に行くことに耐えられるのだろうか。 一瞬にして移動出来る手段を持つなら、行っても良いが、育ち盛りの子どもと、新築のマンションを置いては、絶対に幕張を離れたくない。 それに、こいつら、同じ部署にいた上司に対し、何の恩義も感じないのだろうか。日頃から嫌っている俺は別として、お世辞の限りを尽くしていた割りには、薄情過ぎやしないか。 もっとも、会社なんて、そんなところだ。 組織とは言いながらも、最終的には私利私欲を肥やそうとしている人間が集まっているだけのことなんだ。 黒田部長は、そんな薄情な集団の犠牲者なのかもしれない。 それが顕著に表れたのが、その東京本社に立ち寄った時の、皆の視線だった。 俺は、その日のことを良く覚えている。 それは、十月の初旬、銀行筋から後任の部長が我々のコンシュマーサポート課に配属された時に重なった。簡単な就任挨拶が終わって、一同仕事に取り掛かったあたりで、黒田部長が部屋に入ってきた。 後任の部長は一瞥し、簡単な会釈程度を交わしただけだった。前任者が誰であれ、関係無いといった素振りであった。俺の課にも近づいてきたが、課長の挨拶も社交辞令であった。 人間、勢いがある時と、そうでない時があるのだろうか、以前の脂ぎったところさえ無くなっているような気さえした。 黒田部長は、俺に近づいてきた。  「小野寺君、私のデスクにあったパソコンを知らないだろうか。」あまりの小声で聞き取りにくい。俺は、少し同情し始めたが、周囲の物珍しげな視線が厄介だった為、わざと電卓を叩く音を大きくし、聞こえないふりをした。約百名がひしめき合っているフロアの元最高権力者が、肩書きも無い一社員に声を掛けてくるのだ。きっと何事だろうと、耳をそばだてているに違いない。 「小野寺君、私のデスクにあったパソコンを知らないだろうか。」あまりの小声で聞き取りにくい。俺は、少し同情し始めたが、周囲の物珍しげな視線が厄介だった為、わざと電卓を叩く音を大きくし、聞こえないふりをした。約百名がひしめき合っているフロアの元最高権力者が、肩書きも無い一社員に声を掛けてくるのだ。きっと何事だろうと、耳をそばだてているに違いない。「小野寺君。」部長は腰を屈め、座っている俺の耳もとで小声で叫んだ。 「あ、部長、今日はこちらでしたか。」俺は、いかにも芝居がかった大袈裟なジェスチャーをした。 「ああ、残していった書類がまだあったので、取りに戻ってきた。」やっと取り合ってもらえた安堵感が漂う力無い笑顔を見せた。 「そうですか、荷物は、資料室に保管されている筈ですが。」俺は、電卓を叩くのを止め、愛想笑いをしてみた。うるせえなと、いう言葉を後に続けたかったが、ぐっと飲み込んだ。しかも、愛想笑いも苦手なので、一刻も早く部長には立ち去って欲しかった。 「だが、資料室に行ったら、肝心なものが無い。」 「肝心なものって?」 「パソコンだよ。例の。」 「例のパソコンというと、デスクの乗っていた、古い奴ですよね。」 実は、例のパソコンと俺は深い関係にある。部長の転勤後、残っていたデータを覗き見したことがあった。人間を電送する方法という興味深いタイトルのホームページのURLが履歴に残っていたからだ。 「あれは、もともと会社のものだが、中身は私の資産だ。」どこへ怒りをぶつけるわけでもないのだが、部長は困り果てていた。 いい気味だ。身辺整理も出来ないくせに、俺を散々コケにしやがった天罰だ。 「おっしゃることは解ります。バックアップを取っていなかったんですか。だとしたら、致命傷ですよ。第一、型が古くて、下取りも利きませんから、廃棄処分になったんじゃないですかね。庶務課の下川さんなら知ってるはずですよ。聞いてみましょうか。」俺は、話しているうちに、段々テンションが上がってゆくのを感じた。 それは、そのパソコンを使い、こっそり他人の私生活を覗き見していることへの後ろめたさからだろう。それとも、俺がそのパソコンに興味を示したことを見抜いていたのだろうか。 「う、ううん、い、いいんだ。まあ、大したデータでは無い。」部長は、額に汗を薄っすら浮かべ、それを隠すように微笑んだ。 そして、片手で小さく手刀を切り、すまなそうに立ち去った。気の毒だったが、俺は何事も無かったように、再び電卓を叩き始めた。 ここへ入るのは、二重のロックを解除しなくてはならない。一つは、深夜に残業を装い、部長のパソコンから必死操作し、盗み、解明した。もう一つは、自宅にURLを移植し、これもまた解明した。 パスワードは、ベイタウン中年バンドというグループのオリジナル曲のメロディにあった。主旋律の音階のABCを並べてゆくと、見事にそれがパスワードに繋がった。ひょっとしたら、ドレミを、そのままABCに置き換えてゆくものだと思ったが、音楽をやっている者なら、通常の「ド」の音が「C」の音だということが解る。その辺り、巧みに設定したパスワードだったかもしれないが、部長より俺のほうが一枚上手だったのだ。もう一つのパスワードは、ここまで解明できたのだから簡単だろうと高を括っていたものの、二ヶ月の期間を要した。 ベイタウン中年バンドのその曲は、「新検見川ブルース」というヘンテコな題名だが、単純な繰り返しで、どこが良いのか俺には理解出来ない。  こんな曲を、地域活動の一環だと言わんばかりに演奏する中年バンドの人格を疑ってしまう。住民だっていい迷惑だ。そのつまらない繰り返しの中に一つめのパスワードがあった。 こんな曲を、地域活動の一環だと言わんばかりに演奏する中年バンドの人格を疑ってしまう。住民だっていい迷惑だ。そのつまらない繰り返しの中に一つめのパスワードがあった。パスワードが簡単なのも、心理的に不安かもしれないが、忘れてしまう危惧もあるのが人間だ。複雑を極めるパスワードは、ロックを掛けた本人ですら思い出せなくなってしまうからだ。俺は、絶対に同じ曲の中に二つ目のパスワードがあるに違いない、と踏んでいた。 その勘は、見事的中した。どうして気付かなかったのか、不思議なくらい簡単なことだった。最初のパスワードは、「しんけみがわ、まくはり」と繰り返す音階の十文字のアルファベットだったが、二つ目は、「SNKMGW、MKHR」だった。 これは、単純にローマ字を並べ母音を抜いたものだったのだ。一つめのパスワードが音階だった為、返って難しく考えてしまったのだ。しかし、とうとう俺は二つのパスワードを手中に収めたのだ。何事も中途半端で放り投げ、何かを成し遂げるという喜びを知らない俺は、非常に感動していた。 気の利いた飾りも無く、トップ画面に「人間を電送する方法」としか書かれていなかった。 色とりどりのバナー広告が貼り付いていたり、巧妙にデザイン化されたレイアウトであれば、SF小説等の評論ページか、あるいは、つまらない映画の宣伝だと思ったであろう。だが、単純な明朝体で書かれた文字に、独特の緊迫感が漂っていた。適当に辿り着いたネットサーファーを拒絶する雰囲気だ。 その文字をクリックすると、例のパスワード入力画面が立ち上がる。これは、会員専用のホームページには良くあるケースだ。パスワードを知らない部外者は、そこから先に進めない仕掛けになっている。しかも、第一関門のパスワードが解けても、再び同様なパスワード画面が立ち上がる。セキュリティは、完璧なのだ。 くだらない小説だとか、映画のページなら、パスワードを何も二重にすることは有り得ない。 おそらく、相当重要な内容が書かれていることは間違いのないことであった。 不思議なのは、なぜそんな重要な事柄を、誰かが覗く可能性を秘めているウェブの世界に置いてあるのかということだ。 もちろん、この情報を予めパスワードを教えられ、入室を許された複数人が別々のところからアクセスして閲覧できるのは解る。 だが、限られた人数なら、MOや、FDの記憶媒体に入れ配布するほうが、安全性が圧倒的に高いのではないか。 それとも、配布するのに殺人的なパワーを必要とするくらの大人数が対象なのか。 待てよ、そうではない。ある程度、覗かれる意思を持ったホームページなのだ。 それが証拠にパスワードを通り抜けた最初のページに、「ようこそ、人間電送マシーンへ」と書かれている。 限られた人間だけが対象だったら、「ようこそ」というべきではないだろう。おまけに、主宰者の書いたのであろう稚筆な狸の絵がポンポコと腹鼓を打ちながら動くアニメになっている。 これだけ難解なパスワードを解明し、労力を使った割りには、あまりにも馬鹿げた出迎えである。しかも、その狸の股間の大きな二つの物体が左右に動くのだ。まさにナメているとしか言いようが無い。 俺は、最初にこの狸の馬鹿踊りを見た瞬間、長い間取り組んできた大きな仕事がボツになった時のような激しい倦怠感に襲われた。 あるいは、一つ一つの謎を解明しながら次の部屋に進んで行く、アドベンチャーゲームの楽しさが、一気に興ざめしたような感じだった。 激しい怒りにマウスを放り投げ、椅子を立とうとして画面を見た俺は、ポインターが狸の股間を指しているのに気付いた。 読者諸君は、ご承知の通り、マウスのポインターは矢印の形をしている。 俺には、悪魔の尻尾のように見える。 その矢印が、狸の股間に揺れ動く二つの物体を、今まさに刺そうとしているのだ。 人間の心理というか、俺の精神状態がそうさせたのか、再びマウスを持った俺は、悪魔の尻尾で思い切り狸の股間を突っついてみた。 すると、狸の表情が複雑に変化し、「いてぇっ!」とか、「なにすんのや!」という吹き出しが出るのだ。 これは、面白い。俺は、すっかり機嫌を直し、この狸いじめに没頭していた。  の狸と出会ってから何度目かの日曜日、俺はいつもの狸いじめを始めていた。 の狸と出会ってから何度目かの日曜日、俺はいつもの狸いじめを始めていた。そろそろ飽きてはいたが、微妙な突つき方で、狸の台詞と表情が変化する。台詞は、数十種類用意されているようで、「そんなことしたらあかん」とか、「なにさらしとんじゃ」という凝ったものまである。ストレス解消には打ってつけだ。 そうは言っても、多少はこの狸に同情していた。考えてみれば、この狸はまさに自分を映す鏡だ。年がら年中、腹鼓を打ちながら踊らされ、時々上司に小突かれる。そして、痛いとも言えず、再び踊らされる。つまらない理由で、俺を怒鳴りつけていた黒田部長も、きっとストレス解消だったのか。そう考えると、いつまでもこの狸をPCの中で踊らせておくのが可愛そうになってきた。折角出会った狸だが、そろそろ抹消しようと思った。 だが、付き合って間もない恋人どうしが、わけもなく別れてしまうような一抹の寂しさと伴った。 最後にもう一度だけ股間を突っついてみた。 その時だった。 いつもの吹き出しの中に小さなURLのアルファベットが並んだ。それは、一瞬だったが、確かに「http」から始まるアルファベットだった。ご承知のとおり、URLは、ホームページのアドレスだ。そのURLをクリックすれば、別のホームページにジャンプする。つまり、この狸は、URLを伝えるメッセンジャーだったのだ。くだらない狸だと思わせる更なる細工があったのだ。俺は、俄然やる気になってきた。人間を電送する方法は、この狸が本当の入り口だったのだ。それから、どのくらい時間が経過したのか解らない。とにかく、狸の股間を突いて、突きまくった。だが、二度と、そのURLは出なかった。 「あなた、日曜日くらいパソコンばっかりやってないで、こども連れて公園でも行って下さいよ。」振り向いたら、そこには化粧っ気もない妻がやりきれないといった表情で立ちつくしていた。 「そうだな、最近、どつぼにハマっちゃって。」俺は、慌てて狸の画面を閉じた。 「なんか、変な絵が踊ってたみたいだけど。」妻は、俺が仕事をしているのではなく、単に遊んでいるのを見抜いたように嫌味な言い方をした。 「い、いや、たまたま仕事の関係で、ネットの検索していたら、変なサイトに出会っちまったんだ。ほんと、くだらない。まいった、まいった。」苦笑いをしながら、俺は、立ち上がった。 今更ながら、妻の視線を逸らす作戦だった。 「そうですか。私、これから買い物に行かなくちゃならないので、お昼は、ローズベイハーツかなにかで済ませてもらえません?」 「ん、それはいいけど、日曜日ってランチやってたっけ。」俺は、吐き出すように言ったその瞬間、急に脳味噌が異常なスピードで回転し始めたのを感じた。ランチは、日替わりだ。つまり、メニューが替わる。ひょっとすると、狸の台詞も突付き方ではなく、時間帯で変わるのではないか。あるいは、曜日とかで。 「とにかく、出掛けますから、適当に外食して下さいね。」憮然として立ち去る妻を尻目に、俺は再びいつもの狸を開いていた。 イタリア料理独特のオリーブオイルとハーブの香りが漂い、ジャズが流れている俺好みの店だ。 二人の息子は、食欲旺盛で、俺のスパゲティも平らげて、腹が減ったと騒ぎ始めていた。仕方無いので、マスターに、もう一つ追加のオーダーを出そうと思った時、入り口から見慣れた顔が入ってきて俺達のテーブルのすぐ近くに座った。 俺は、はっとした。 そして次の瞬間、全身の血が一瞬にして凍る思いだった。ウィスキーの氷も、これくらい早く凍ってくれると有り難い。うちの冷蔵庫は、値切って買ったわけではないが、性能が悪すぎる。そんなことは、どうでもよい。俺の視線は、鹿児島にいる筈の黒田部長を捕らえていた。 確か、クリスマスまでは絶対戻らないと言っていたのだ。 「やあ、食事かな?」部長は軽い会釈をし、薄ら笑いを浮かべていた。 「え、ええ、ちょっと子どもの面倒を頼まれたもんで。」俺は、返事をするのがやっとだった。 どうして、ここに部長がいるのか、一刻も早く理由を聞きたかった。もちろん、大嫌いな人物なので、理由が分かれば用は無い。 「これは、これは、お子さんも。ちょっと見ない間に大きくなったもんだ。いいよね、実に。このくらいの子どもは一番可愛い。うちのなんか、駄目だ。高校に通うようになると、親を無視するからね。今日も、メシを誘ったのに断られた。ははは。」そう言いながら部長は、ろくにメニューも見ないで、ウェイトレスにエスプレッソを注文した。 俺は、しどろもどろで、返事が出来なかった。 「ねえ、もう頼んだの。おなか減ったよ。」小学校二年の上の息子が叫んだ。 「ああ、そうだった。」俺は、カウンターから外に出て、他の客と話をしているマスターが目に止まったので、手招きし、追加のスパゲティを注文した。 「小野寺君、何か驚いているようだけども、私が突然ベイタウンに戻っているからかな?」再び、部長が尋ねた。なにかを探るような目付きだった。 「ええ、実は、そうなんです。確か鹿児島からは、暫く戻られないとお聞きしていたもので。一体、何かあったのですか。」 「ははは。やはり、そんなところか。まあ、無理も無い。先々週戻ってきたばかりだし、会社にも帰郷するなんて一言も言っていない。お忍びってわけでもないんだが。」部長は、取り付く島の無いスピードで話始めた。 「しかし、小野寺君、飛行機は便利だよ。そりゃ、安月給だから、そう、しょっちゅう戻るわけにはいかんがね。でも、こうやって、日曜日にベイタウンで美味いコーヒーが飲めるってわけだ。」 「お父さん。この人誰?」幼稚園の年長の下の息子が大きな声を出す。 「ああ、お父さんの・・・。」 「ははは、こりゃ、失礼。ぼく、おじさんはね、君のお父さんと一緒に仕事していたんだ。」部長は、とてつもなく上機嫌で、今度は息子と話し始めた。 「今は左遷されたんだよ。ざまあ見さらせっ。」と、俺は息子に声にならない声で続きを喋っていた。 どきどきしながらも、レスポンスが良いのは、気持ちが高ぶっているせいだ。現に、猛烈な勢いで心臓の鼓動が脳味噌のてっぺんまで伝わってくる。俺は、驚愕している自分が、どういう原因によってかということを大体想像していた。そうだ、飛行機ではない。けちな部長が、自腹を切って飛行機に乗り、わざわざコーヒーを飲むために戻ってくるわけがない。 だとすると、何故ベイタウンにいるのだろう。それは、解っている筈なんだ。だが、認めたくない。解っていても認めるもんか。馬鹿な、そんな馬鹿げている。人間が電送されるなんて、絶対に認めない。どうかしている。俺はどうかしているのだ。 力を込めて偶然手に持ったタンブラーを握りしめたが、ドラマのようには割れなかった。俺は、意外に握力が弱いのだ。それに、本当に割れ、痛い思いをするのも嫌だった。代わりに、水がこぼれる。 「冷たいっ!お父さん、冷たいなあ、びしゃびしゃになっちゃたよ。」一旦、テーブルにバウンドした雫が、下の息子の膝に垂れたのだ。 「そのくらいのことで、騒ぐな。」俺は、はっとしながら、すぐさま冷静を装い、持っていたハンカチで息子の膝を拭いた。 「小野寺君、疲れているみたいだな。はははは。仕事のし過ぎじゃないかな。気をつけなさいよ。働き過ぎは、私みたいな年齢になると、身体に出るからね。」部長は、コーヒーをすすりながら、俺を横目で見つめていた。だが、何かに気づいているようにも思えた。 俺は、息苦しくなってきた。一刻も早く、この場を去ることばかりを考えていた。 「さ、早く食べないと、お母さんが帰ってくるよ。」俺は、息子たちを急かした。 「だって、まだスパゲティ、来てないよ。」二人の息子が同時に俺を睨んだ。まったく気が利かないガキどもである。 「そうか、そ、そうだったね。じゃあ、お父さんは、ちょっと、迎えに行ってこようかな。」 「へえ、でもさ、お母さん、夕方まで戻らないって言ってたよ。」今度は、上の息子。 「ああ、そうだったけ、お父さん、そそっかしいからな。わはははは。あーあ。」俺は、もう何がなんだか分からなくなってきた。まるで、つるつる滑る氷の上を思い切り走っているような気分だった。あるいは、とてつもなく大きな蟻地獄に落ちてしまったようでもあった。 「小野寺君。最近、私はホームページに凝っていてね。」突然、部長が話題を切り替えた。 「はあ、そうですか。何か面白いことでもあったんですか。」 「面白いとも。自分の作ったものに、色々な人がアクセスしてくるんだよ。」 「そうですね。」  「私が作ったホームページになんて、何の役にも立たないから、誰もアクセスしないと思っていたのだが。」部長が再び俺の顔を覗き込んだ。 「私が作ったホームページになんて、何の役にも立たないから、誰もアクセスしないと思っていたのだが。」部長が再び俺の顔を覗き込んだ。「人気が出てきたんですね。」 「いや、アクセスは一人だけだ。しかも、このベイタウンからね。」 部長が言い終わるか、否や、俺は無意識に勢い良く席を立った。これほど人の言葉で過敏に身体が反応したのは、高校の時、万引きしたのが親にバレて以来だろう。しかし、タイミングは最悪だった。 ちょうどウェイトレスがスパゲティをテーブルに置こうとしたのと交錯したので、その皿は、宙に舞い上がる。そして、まるでスローモーションを見ているように、俺の頭に不時着した。にんにくと、ハーブの良い香りと共に歯ごたえのある自慢のパスタが、スダレのようにゆっくりと、俺の顔面を滑り落ちてきた。
| ||
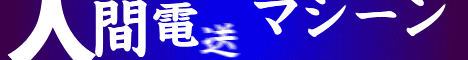 ◇リレー小説・人間電送マシーンPart2◇ [第1話へ] [第3話へ] ―人間電送マシーンは、毎回の続きを読者からの寄稿で構成するリレー小説です。― あなたも人間電送マシーンを書いてみませんか?詳しくはshibazax@mb.infoweb.ne.jpまで Copyright(C) 2000-2001Oretachi'sHP All rights reserved. oretachi@ml-c6.infoseek.co.jp |

