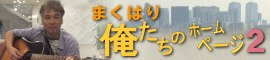この季節、どうしても私は父の死を思い出さずにはいられない。ベイタウンにイルミネーションが輝く頃に父が他界した。今から9年前だから、一般にいう十周忌。父は神式で鬼籍に入ったので、十年祭と言う。あっと言う間の10年だ。インターネットという性格上、あまり、こういうことを書くのもどうかと思うが、父の死のことに少しだけ触れてみたい。やっぱ、死をしょっちゅう意識する年齢になったのかもしれない。(前々回にも似たようなことを書いたな。)
10年前の1997年の晩秋、父は腎臓癌であると診断され、万が一の治癒を期待し、腎臓の摘出手術を受けた。しかし、手術したものの、横隔膜をはじめ、癌は他の臓器にも転移していた。先生は余命3ヶ月と宣告した。それは息子の私だけが聞いた。暫く入院していたものの、最期は畳で死を迎えさせてやりたいと母と私が家に連れて帰った。
年を越し、春が来て、夏になった。余命3ヶ月と言われてからもう半年以上、つまり9ヶ月くらい頑張って父は生きていた。生きながらえていた。しかし、頑張って生きていると言えるかどうか。骨と皮だけになっていた。まさに枯れ木だ。呼吸するのも大変なようだ。体中に痛みがあり、再入院した。痛みを無くす為にモルヒネの頻度も多くなり、精神状態も段々悪くなっていった。秋には、朦朧としていることも多くなった。晩秋、遂に意識が無くなってきた。
1998年、今から9年前の11月の中旬、看護婦さんが「今日から痛み止めの座薬(モルヒネ)を多くします。ということは、今まで以上に眠っている期間が多くなります。起きているのか、寝ているのかも分からなくなります。」と言って、私に同意を求めた。それはもう人間としての機能が殆ど無くなってしまうという意味だった。しかし、同意せずにはいられなかった。
その頃から、私と母が交互に病院に寝泊りした。寝るときは、父のベッドの隣の簡易ベッドである。時々、父は目を覚まし、わけのわからないことを言い、そして、また眠る。ただ、ごくたまに精神状態がきちんとしていることもあって、普通に会話できる。家のこととか、好きな釣りの話をした。ちょうど父が病気になった頃、実家の近くにオープンした釣具店があり、病気が治ったら一緒に行こうなどと話した。「黒鯛を狙いに行きたい。」と父は目を輝かせていた。泣き言は言わなかった。
母が付き添いしているときは、体中の痛みを訴え、「なんでこうなってしまったのか。」とか、「まだまだ死にたくない。」と言って、涙を流したらしい。息子の前では決して泣かない父が最期には妻に甘えたのである。ずっと働きずくめで、やっとこれから老夫婦で色々な場所に旅行に出かけられる年齢になってきたときに、死への旅立ちはさぞや無念であろう。
11月の終わり頃に意識不明になった。今でも時々思い出す死の数時間前の父の表情。呼吸が荒く、目は見開いているものの、焦点が定まらない。話しかけても全く反応が無い。先生は「もう意識はありません。痛みもありません。」と言った。本当なのか。私と父が二人きりになった個室。私が「もういいよ。頑張らなくてもいいよ。」と父の耳元で言った。すると、父は涙を流した。
母は覚悟を決めていた。いざというときに備え、休息を取った。私は夕方まで病院に居て、そして、次の日の仕事に備えて、ベイタウンに戻ってきた。ベイタウンはイルミネーションが輝いていて、綺麗だった。クルマの窓からでも十分楽しめた。妻子は夢のような世界に喜んでいた。ついさっきまでいた病院のあの重苦しい世界とはまったく異なる別世界が広がっていた。私も連日の付き添いで疲れがたまっていた。だから、開放感からか、ほっとした気分だった。父が逝ったのは、そんなときだった。最期は最愛の妻に看取られた。
再び私は木更津に戻った。もちろん、喪服も用意してだ。イルミネーションに輝くベイタウンから、ひょっとしてイルミネーションよりも数倍綺麗な工場地帯を通り抜け、木更津の病院へ向かった。父は長い長い辛い辛い闘病生活からやっと開放されていた。顔に白い布がかけてあった。母はいなかった。荷物などをまとめたり、その他の手続きをしていたのだろう。
深夜、病院の奥の、おそらく一般の人は知らないであろうロータリーに父の遺体は運ばれた。そこには葬儀屋のクルマが待っていた。私はその葬儀屋のクルマを先導する為に、自分のクルマをそのロータリーに入れた。見送りは父のことをよく面倒みてくれた二人の看護婦さんだった。ひとりはインターンだった。まだまだ幼い感じの娘さんだ。父がインターンをしていて初めての患者だったようだ。彼女は泣いていた。泣いてくれていた。私は不思議と悲しくなかった。バックミラーに彼女達が手を合わせてくれているのが見えた。オリオン座をはじめとした冬の星座がまるで落ちてきそうなくらい近くに見えた。
2007/12/21
しばざ記 373 |
 |
|